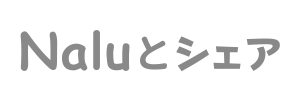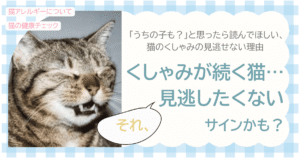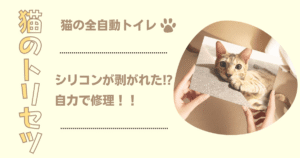猫同士の関係がうまくいかないとき、どちらか一方、または両方の猫に行動の変化が現れることがあります。
威嚇や隠れるだけでなく、そそうや過剰なグルーミングなど、見逃したくないサインも。
この記事では、猫たちの折り合いが悪いときに起きやすい問題行動と、その背景・対処法をわかりやすく解説します。
- 猫同士の折り合いが悪いときに起きる代表的な問題行動について
- 問題行動の背景にある猫の感情やストレスの仕組みについて
- 飼い主ができる対処法や環境の整え方について
- 先住猫と新入り猫の関係改善のヒントについて

猫たちの関係が戦争状態の場合
 nalu
nalu猫たちのこれ以上の関係悪化をふせぐには、まず引き離すことが大切です!
いがみ合う猫たちはもちろん、人間にもストレスになりますよね。
問題行動が激しくなると、飼い主も不安定に。不安定な飼い主が問題のある猫を扱うと、さらに悪い状況へ。まさに負のループです。
そんな時はまず、猫を引き離して別々の部屋に分けてください。
猫たちの問題が解決するまでは、猫同士が接触しないようにしましょう。
そして、こちら(*記事下部リンクへ飛びます)から、STEPを改めて行ってください。
問題行動は「猫からのSOS」気づいてあげることが第一歩
猫は言葉を話せないぶん、行動で気持ちを伝えます。
折り合いが悪いときに見られる行動は、猫からの「助けて!」のサインかもしれません。


猫のストレスサインを見逃さないために
猫はストレスを感じると、普段と違う仕草や行動が現れます。
「なんとなく様子がおかしいかも…」と感じたら、以下のようなサインをチェックしてみましょう。
しっぽが膨らむ、耳が横に倒れるなどのボディランゲージ
しっぽが大きく膨らんでいるときは、驚きや恐怖、警戒心が強くなっているサイン。
耳が横に倒れているときは、緊張や不安を感じている可能性があります。
こうしたサインが頻繁に見られる場合は、猫同士の関係や環境にストレスがあるかもしれません。
猫のボディランゲージを知るにはこちらの記事がおすすめです。
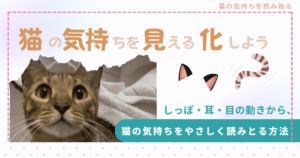
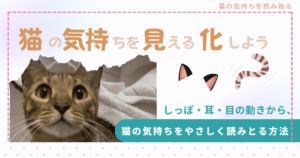
隠れる時間が増える、寝る場所が変わる
いつも寝ていた場所に行かなくなったり、家具の隙間や押し入れに隠れる時間が増えたら、何かに不安を感じているサインかもしれません。
特に新入り猫との関係がうまくいっていないときは、先住猫が「居場所を奪われた」と感じてしまうこともあります。
鳴き声が増える、逆に鳴かなくなる
鳴き声が多くなるのは、何かを訴えている可能性があります。
逆に、いつもよく鳴いていた猫が急に静かになるのも、ストレスや不安のサイン。
鳴き方の変化は、猫の心の変化を知る大切なヒントです。
こうしたサインを見逃さず、猫の気持ちに寄り添うことで、問題行動の予防や関係改善にもつながります。
「なんとなく違うかも」と感じたときこそ、猫の表情や仕草をじっくり観察してみましょう。
よくある問題行動とその理由
- トイレ以外での排泄(そそう)
→縄張りの不安、ストレスによるマーキング - 過剰なグルーミング(毛づくろい)
→緊張や不安の発散、自己安定行動 - 食欲不振・嘔吐・下痢
→ストレスによる体調不良 - 威嚇・唸り・追いかけ回し
→縄張り争い、相手への警戒心
問題行動の理由をもう少し詳しく
猫の問題行動は、単なる「困った行動」ではなく、環境や感情の変化に対する反応です。
ここでは、よくある行動の背景をもう少し丁寧に解説します。
トイレ以外での排泄(そそう)
縄張りへの不安やストレスが原因で、トイレ以外の場所で排泄してしまうことがあります。
特に新入り猫が来た直後は、先住猫が「自分の場所を守らなきゃ」と感じて、マーキングのような行動を取ることも。
トイレの数や配置、猫同士の距離感を見直すことで改善するケースもあります。
過剰なグルーミング(毛づくろい)
リラックスのための毛づくろいが、過剰になるとストレスのサイン。
同じ場所ばかり舐めて、毛が抜けたり皮膚が赤くなることもあります。



ぼくは、飼い主さんが体調が悪くて遊んでもらえなかったときに、ハゲをつくってしまいました。
食欲不振・嘔吐・下痢
猫はストレスが体調に出やすい動物です。
環境の変化や猫同士の不仲が原因で、食欲が落ちたり、消化不良を起こすことがあります。一時的なものであれば様子見でも構いませんが、数日続く場合は獣医師の診察をおすすめします。



ぼくは、分離不安症で、飼い主さんの留守が続くと吐いちゃうことがあるよ。
威嚇・唸り・追いかけ回し
猫同士の関係が不安定なときに、よく見られる行動です。
「シャーッ」と威嚇したり、唸り声をあげたり、相手を追いかけるのは、縄張りを守ろうとする本能的な反応です。
この段階では、無理に仲良くさせようとせず、物理的に距離を取ることが大切です。
猫が安心できる居場所をそれぞれに用意してあげましょう。
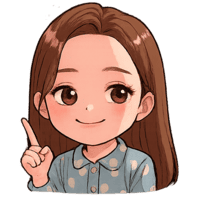
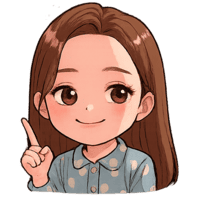
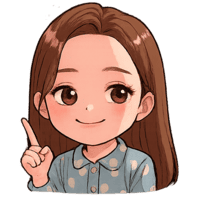
このように、猫の行動には必ず理由があります。
「困ったな」と思う前に、「何か伝えたいことがあるのかも」と考えてみると、猫との関係がぐっと深まりますよ。
飼い主ができる対処法
- それぞれの猫に安心できるスペースを用意する
-
逃げ道と安全な通り道を確保して、待ち伏せのできるような場所をなくしましょう。
- 猫同士の距離を保てるように、居場所を分ける
-
問題が大きい場合は猫同士を引き離しましょう。
- 無理に仲良くさせようとせず、時間をかけて見守る
- 病気で痛みなどがある可能性も視野に入れてみる
- フェリウェイなどの猫用フェロモン製品を活用する
フェリウェイとは?
フェリウェイは、猫の不安やストレスを和らげるために作られた製品です。
フェリウェイについて 詳しくはこちら
仕組み
フェリウェイは、猫が顔をこすりつける行動で分泌するフェイシャルフェロモン(特にF3フェロモンという安心感を与える成分)を人工的に合成したものを主成分としています。
この合成フェロモンを拡散器(コンセントに差すタイプが多い)などからお部屋に広げることで、猫に「ここは安全で安心できる場所だ」と感じさせ、ストレスを軽減する効果が期待されます。
主な用途
以下のような、猫がストレスを感じやすい状況でよく使用されます。
- 引っ越しや模様替えなどの環境の変化
- 新しいペットや家族を迎えたとき
- 動物病院への移動や受診
- スプレー行動(おしっこをかける行為)や過剰なグルーミングなどの問題行動の軽減
どれもうまくいかないときに試してみてほしいこと


対面ステップ(やり直しも含め)をきちんとやり通したのに、猫たちの関係が悪化した。。相性が悪いのかな?と決めてしまう前に試してほしいことがあります。
対面ステップをやりなおす
すでにやり直していたとしても、飛ばしたSTEPや手抜きがなかったか振り返ってみましょう。
「この猫たちは合わないのかも…」と決めてしまう前に、徹底的な再引き合わせをもう一度試してみてください。
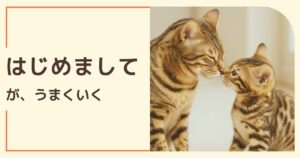
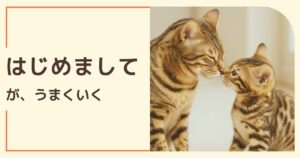
遊びと食事で関係をリセットする
対面ステップが終わったら、猫たちを同じ部屋に入れて、相手に集中させないように遊びに誘ってみましょう。
猫の頭数分の人間が同時に遊びに夢中にさせてあげると、さらに効果的です。
最初は、遊びに集中できないかもしれませんが、少しずつ慣れてくると、遊びの時間が長く続くようになります。
そうなったら、たっぷり遊んだ後に、同じ部屋でフードを食べさせてみましょう。
この「遊び→食事」の流れを繰り返すことで、猫たちの緊張がほぐれ、訓練から日常生活へと自然に移行していきます。
薬物治療という選択肢もある
安易におすすめするものではありませんが、猫の苦しみを和らげるために、薬物治療が必要になる場合もあります。
刺激に対する攻撃的な反応や、過度におびえる反応を緩和する効果が期待されます。
ただし、薬の使用は自己判断ではなく、必ず獣医師に相談してください。
猫の体質や年齢、健康状態によっては、薬が適さない場合もあります。
天然療法や代替ケアも選択肢に
- 天然の治療薬
- 針治療
- クラニオセイクラルセラピー(頭蓋仙骨療法)
軽いタッチによる力を加えることで心身の不調をいやす
これらの療法も、獣医師や専門家の指導のもとで行うことが大切です。
まとめ
- 猫同士の折り合いが悪いとき、行動に変化が現れることがある
- 問題行動は猫からのSOS。背景にある感情を理解することが大切
- 飼い主ができる対処法で、猫の安心感を取り戻すことができる
- 関係改善には時間がかかることも。焦らず、猫のペースを尊重して
猫たちの「困った行動」は、実は「困っている気持ち」の表れです(病気が要因の場合を除く)。
気づいてあげることで、対処法も見えてきて、いずれ解決に向かっていきます。
失敗にめげず、うまくいっていた頃の状況から、もう一度やりなおしてみてくださいね。