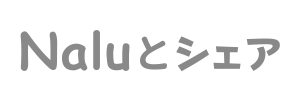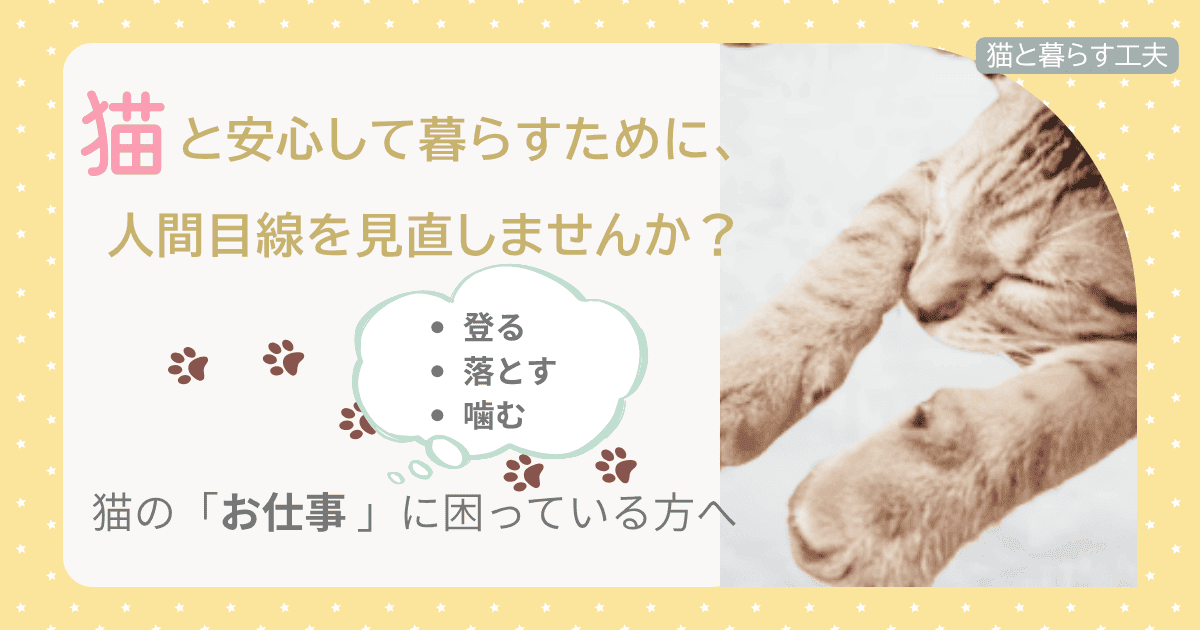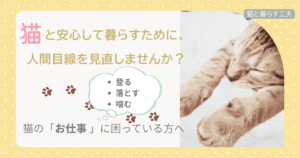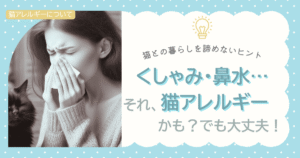猫を迎えるということは、ただペットを飼うということではありません。
それは、自分の部屋が“猫の家”になる日。
あなたの暮らしの主役が、ふわふわの小さな探検家にバトンタッチされる瞬間です。
キッチンの棚の上に飾ったお気に入りの雑貨。
それは猫にとっては「通行の邪魔」
だから、落とされても怒らない覚悟が必要です。
それは“猫が悪い”のではなく、“そこに置いた人間の責任”なのです。
登らせないか、置かないか。
この選択が、猫との平和な共存の第一歩。
今回は、そんな「猫目線」で見直したい、お部屋の環境対策についてお届けします。
猫と人が心地よく暮らすための、ちょっとした工夫と、ほんの少しの覚悟。
でもそれは、きっと楽しくて、愛おしい日々の始まりです。
はじめに:猫の目線で部屋を見直すということ

猫は、私たちが思っている以上に自由で、好奇心旺盛な生き物です。
高いところにも軽々と登り、狭い隙間にもスルリと入り込み、気になるものにはすぐに手(前足)を伸ばします。
そんな猫たちと暮らすには、「人間目線の部屋づくり」から「猫目線の環境づくり」へと、少しだけ視点を変える必要があります。
たとえば、飾り棚の上に置いたお気に入りの雑貨。
それは猫にとって、ただの“通行の邪魔”。
だから、落とされても仕方ない。むしろ「そこに置いた人間の責任」と割り切る覚悟が必要です。
猫にとって快適な空間とは、危険が少なく、自由に動けて、安心して過ごせる場所。
そのためには、家具の配置や床材、窓の安全性、電気コードの扱いなど、細かな部分まで見直すことが大切です。
この記事では、猫を迎える前にチェックしておきたい「お部屋の環境対策」について、具体的なポイントを紹介していきます。
猫との暮らしがもっと楽しく、もっと安心になるように。
小さな工夫が、大きな安心につながります。
片づけておくべきもの
猫の誤解を防ぐために
猫は、見慣れないものに興味津々。
そして、気になるものは「触ってみる」「噛んでみる」「落としてみる」ことで確認します。
それは、猫にとっての“お仕事”のようなもの。
だからこそ、誤飲やケガにつながる可能性のあるものは、事前にしっかり片づけておくことが大切です。
観葉植物・花
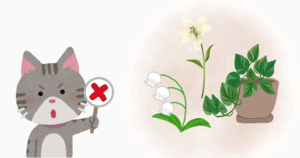
見た目は癒しでも、猫にとっては危険なものも。
ユリ、ポトス、アイビーなど、猫に有害な植物は意外と多く、誤って口にすると命に関わることもあります。
植物を飾るなら「猫に安全な種類」か「猫が届かない場所」に。
わがやでは、ポトス、モンステラなどは、ベランダへ。
代わりにフェニックスロベレニー(ヤシの木)を購入し室内に置きました。
観葉植物やお花の購入は、こちらの診断が便利です!
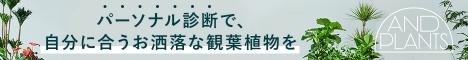
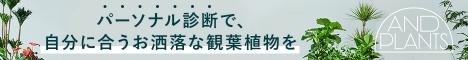
小物・薬品・化粧品類


棚の上に置いたハンドクリームや目薬、アクセサリーなども要注意。
猫は高いところに登るのが得意なので、「届かないだろう」は通用しません。
落として割れる、舐めてしまう、飲み込んでしまう…そんなリスクを減らすためにも、引き出しや収納ボックスにしまっておきましょう。
糸・輪ゴム・ヘアゴムなど
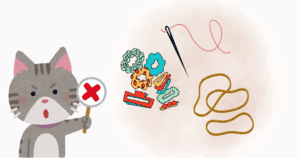
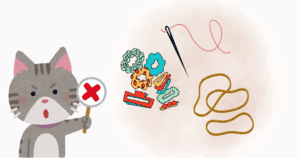
小さくて軽いものほど、猫の“おもちゃ”になりがち。
でも、これらは誤飲の危険性が高く、腸閉塞などの重大なトラブルにつながることも。
遊ばせるなら、猫用のおもちゃを。人間の生活用品は、猫の手の届かない場所へ。
猫との暮らしは、ちょっとした「片づけ」が命を守ることにつながります。
「これは猫にとってどう見えるだろう?」という視点で、部屋の中を見直してみると、意外な発見があるかもしれません。
事例は、こちらの番組で視聴しました。
こちらのジェフ先生は、本当に素晴らしい獣医師さんで、毎回感動しながら視聴しています。


見落としがちな、 猫と暮らす家でのホウ酸団子の安全な設置場所
- 猫が絶対に届かない場所に設置することが最優先
- 床置きはNG:猫の目線・鼻先にあるものはすぐに興味を持ちます
- 設置するなら、“猫が入れない隙間”や“密閉された空間”に
安全な設置場所の例
| 設置場所 | ||
|---|---|---|
| 冷蔵庫や棚の裏側(猫が入れない隙間) | 隙間が狭く、猫が侵入できないことを確認 | |
| キッチンシンク下の扉付収納 | 扉がしっかり閉まることが前提。チャイルドロックがあると安心 | |
| 洗面台下の収納(扉付) | 同上。開けっぱなしにしない習慣をつける | |
| クローゼットの奥(猫が入らない部屋のみ) | クローゼットに猫が入る可能性がある場合は避ける | |
| ベランダの隅(猫が出られない環境の場合) | 完全に猫の立ち入りがない場合に限る |
避けたい場所
- 床の隅や家具の脚元(猫が簡単に見つけてしまう)
- キッチンのオープン棚やカウンター下
- トイレや脱衣所など、猫が自由に出入りできる場所
ホウ酸団子の設置が難しい場合は
- 密閉型のゴキブリ駆除アイテム(猫が開けられないタイプ)
- 天然成分の忌避剤(ハーブ系など)
など、猫に優しい選択肢もあります。
おすすめ駆除剤
ゼロノナイト ゴキブリ・トコジラミ用 1プッシュ式スプレー
プッシュするだけで簡単に使えるタイプ。気になる場所に、いつでも手軽に使用できます。
赤ちゃん、ペットがいるご家庭でも使用できるとのことです。
- ペットの誤食リスクと併せて「使用前に必ず製品ラベルを確認」してくださいね。
窓・網戸の安全対策
外の世界は魅力と危険がいっぱい


猫は、外の景色を見るのが大好き。
鳥の声、風に揺れる葉、通り過ぎる人や車…窓の外は、猫にとってまるで映画館のような場所です。
でもその「映画館」には、思わぬ危険が潜んでいることも。
網戸は“押せば開く”ことを猫はすぐに学ぶ
網戸は、猫にとって「ちょっと押してみようかな?」の対象。
特に軽いタイプの網戸は、前足で押しただけで外れてしまうこともあります。
網戸ロックやストッパーを設置することで、脱走や落下のリスクを大きく減らせます。
窓の開け方にも注意
「少しだけ開けておけば風通しがいい」
…その“少し”が猫にとっては十分な隙間。
頭や体を無理に押し込んで外に出ようとすることもあるため、窓の開閉は「猫が通れない幅」を意識して。
ねこは、顔の大きさ程度の隙間(約6cm未満)があればすり抜けられるよ
より確実に脱走を防ぐには、4.5cm以下の隙間に、顔の横幅が狭い猫や子猫は、より小さい隙間でも通り抜けられることがあるので注意してくださいね。
夏場の熱中症対策にも
窓を開けて風を通すことは、室温管理にも大切。
でも、網戸越しの直射日光や、締め切った部屋の熱気がこもると、猫も熱中症になることがあります。
遮光カーテンや風の通り道を工夫して、快適な空間づくりを。
猫は、思いがけない行動をするもの。
「うちの子は大丈夫」と思っていても、ある日突然、網戸を開けてしまうことも。
だからこそ、先回りして“安全な窓まわり”を整えておくことが、猫との安心な暮らしへの第一歩です。
フローリング・床材の見直し
滑る床は猫にとって危険地帯
猫はしなやかで身軽な動物ですが、実は関節や足腰に負担がかかりやすい一面もあります。
特に、ツルツルしたフローリングの上では、走ったりジャンプしたりするたびに滑ってしまい、ケガの原因になることも。
滑りやすい床は関節に負担
人間にとっては快適でも、猫にとっては“スリップゾーン”。
特に子猫やシニア猫は、踏ん張りがきかず転倒しやすくなります。
滑り止め効果のあるマットやラグを敷くことで、安心して走り回れる空間に。
掃除のしやすさ vs 毛の絡みにくさ
猫の抜け毛や砂の飛び散りなど、床には日々の“猫の痕跡”が残ります。
毛が絡みにくく、掃除しやすい素材を選びつつ、滑りにくさも両立できる床材が理想です。
撥水性のあるラグや、洗えるマットなどもおすすめ。
クッション性のある素材で安心感を
フローリングの上にクッション性のあるマットを敷くことで、ジャンプの着地時の衝撃を和らげることができます。
特にキャットタワーや棚の下など、猫がよく飛び降りる場所には重点的に敷いておくと◎。
猫の足元環境は、見落としがちだけどとても大切なポイント。
「滑らない」「痛くない」「掃除しやすい」この3つのバランスを意識することで、猫も人も快適に過ごせる空間になります。
我が家でも以下のようなタイルカーペットで対応しています。
【日本製】 サンコー ずれない タイルカーペット
撥水加工だから、汚れもサッと一拭きできて、洗濯機OK(洗濯ネット併用・繰り返し使えます)、床暖房対応(推奨:低温)、ハサミでカットも可能です。
カラーも20色以上から選べます。
電気配線・コード類の工夫


噛みたい欲から守るために
猫は、細くて動くものが大好き。
だから、電気コードや充電ケーブルは“おもちゃ”に見えてしまうこともあります。
でもそれは、感電や火災などの重大な事故につながる危険な遊び。
猫の安全を守るためには、コード類の扱い方をしっかり見直す必要があります。
噛み癖がある猫は特に注意
子猫や若い猫は、歯のむずがゆさからコードを噛むことがあります。
感電のリスクだけでなく、コードが断線して家電が故障することも。
コードカバーやスパイラルチューブで保護することで、噛みづらく・見えづらくする工夫を。
配線ボックスで“隠す”という選択
テレビ裏やPC周りなど、コードが集中する場所には配線ボックスが便利。
見た目もスッキリし、猫の手が届かない構造になっているものを選ぶと安心です。
床にコードが這っている状態は、猫にとって“狩りの対象”になりがちなので、なるべく浮かせる・まとめる工夫を。
コンセント周りの安全対策
コンセントにホコリが溜まると、トラッキング火災の原因にも。
猫がコンセントに触れてしまうこともあるので、未使用の差込口にはキャップをつけるなどの対策を。
また、コンセント付近に水や猫のトイレを置かないようにするのも基本です。
猫との暮らしでは、「見えない危険」をいかに減らすかがポイント。
コード類は、猫の好奇心をくすぐる“罠”になりやすいからこそ、先回りして守る工夫が必要です。
安全な配線環境は、猫にも人にもストレスの少ない空間づくりにつながります。
壁・棚のインテリア雑貨
飾るより落とさないを優先する暮らし
猫は高いところが大好き。
棚の上、冷蔵庫の上、キャビネットの上…「ここは無理だろう」と思う場所にも、気づけばスッと登っていることがあります。
わがやのじゅにあも、キャットタワー→カーテンレール→「エアコンの上」まで探検していることが何度もありキャットタワーの位置を替えることになりました。
猫は“登れる場所”を見つける天才
棚の段差、壁の出っ張り、カーテンレール…猫は、ちょっとした足場を見つけては登ります。
その先にある雑貨や飾り物は、猫にとって「邪魔な障害物」。
だから、落とされても怒らない覚悟が必要です。むしろ「そこに置いた人間の責任」と割り切ることが大切。
落下しやすい雑貨は撤去 or 固定
ガラス製の花瓶、陶器の置物、写真立てなどは、落下すると割れて危険。
どうしても飾りたい場合は、両面テープや耐震ジェルなどでしっかり固定する工夫を。
「飾る場所を変える」「壁掛けにする」など、猫の動線を避ける配置も有効です。
壁面インテリアは“登られる前提”で考える
壁に飾ったポスターや布、タペストリーなども、猫がよじ登る可能性があります。
特に布製品は爪が引っかかりやすく、破れたり落ちたりすることも。
猫が触れない高さに設置するか、登られても安全な素材・固定方法を選びましょう。
猫との暮らしでは、「飾る楽しみ」と「安全な空間づくり」のバランスが大切。
“落とされてもいいものだけ飾る”という潔さが、猫との平和な共存につながります。
インテリアは、猫と一緒に暮らすからこそ、もっと工夫できる余地があるのかもしれません。
お風呂・水回りの事故防止
ちょっとした油断が命取りになることも
猫は水が苦手…と思われがちですが、実は好奇心から水場に近づく子も少なくありません。
特に浴室や洗面所などの水回りは、猫にとって「ひんやりしていて面白そうな場所」。
でもその“面白さ”の裏には、思わぬ危険が潜んでいます。
普段は浴室には入らないけど、お風呂について行ってフタの上で、待ってる時に動いたら滑って浴槽に落ちたことがあるんだ
あれは災難だったね!ついでにシャンプーする事にもなったしw
浴槽の水は残さない
お風呂の残り湯に猫が落ちてしまう事故は、実際に報告されています。
猫は静かに忍び込むので、気づいたときにはすでに浴槽の中…ということも。
入浴後は必ず水を抜き、浴室のドアはしっかり閉めておく習慣を。
ドアの開閉管理を徹底する
猫は器用にドアを開けることがあります。
引き戸や軽いドアは、前足で押したり引いたりして開けてしまうことも。
浴室や洗面所のドアには、簡易ロックやドアストッパーを設置して、猫の侵入を防ぎましょう。
洗剤・シャンプー類の誤飲に注意
水回りには、洗剤やシャンプーなどの化学製品が置かれていることが多く、猫が舐めてしまうと中毒の危険があります。
ボトルはしっかりフタを閉め、猫の手が届かない棚や収納にしまうことが基本です。
水回りは、猫にとって“涼しくて静かな隠れ家”にもなりがち。
でも、そこには滑りやすさ・水・薬品など、危険がいっぱい。
「ちょっとくらい大丈夫だろう」が、命に関わる事故につながることもあるからこそ、日々の習慣と環境づくりが大切です。
侵入されたくない部屋の対策


ドアは閉めたでは通用しない⁉
猫は、静かに、そして器用に行動する達人。
「この部屋には入れないはず」と思っていても、いつの間にかドアを開けて侵入している…そんな経験をした飼い主さんも多いのではないでしょうか。
猫はドアの開け方を覚える
引き戸や軽いドアは、前足で押したり引いたりして開けてしまうことがあります。
特に好奇心旺盛な猫は、何度もチャレンジして“開け方”を習得することも。
「閉めたつもり」ではなく、「開けられないようにする」ことが大切です。
ぼくも、引き戸は得意です!
ドアストッパーや簡易ロックの活用
市販のドアストッパーやチャイルドロックを使えば、猫の力では開けられないようにできます。
引き戸には“すき間防止テープ”や“戸当たり棒”なども有効。
ドアノブタイプの場合は、ノブカバーや上部に鍵をつける工夫も。
立ち入り禁止部屋の境界づくり
どうしても入ってほしくない部屋(寝室、作業部屋など)がある場合は、
- フェンスやベビーゲートで物理的に遮る
- ドアの前に“苦手な素材”(アルミホイルやザラザラマット)を敷くなど、猫が「入りたくない」と思う工夫も効果的です。
猫は、飼い主の“想定外”を軽々と超えてくる存在。
だからこそ、「入ってほしくない場所」には、しっかりとした対策が必要です。
猫との暮らしは、ちょっとした“境界線の工夫”で、ぐっと快適になります。
まとめ|猫との暮らしは、ちょっとした工夫の積み重ね


猫を迎えるということは、「人間の家に猫が来る」のではなく、「猫の家に人間が住まわせてもらう」くらいの気持ちでちょうどいいのかもしれません。
高いところに登る、狭い隙間に入る、気になるものを落とす…そんな猫の行動は、すべて“自然なこと”。
だからこそ、私たちが先回りして環境を整えることで、猫も人も安心して暮らせる空間が生まれます。
今回ご紹介した環境対策は、どれも「ちょっとした工夫」ばかり。
でもその積み重ねが、猫の命を守り、飼い主の心の余裕につながります。
最後に、簡単なチェックリストを置いておきます。
猫を迎える前に、ぜひお部屋を猫目線で見直してみてください。
- ☐ 有害な植物や小物は片づけた?
- ☐ 網戸や窓の安全対策はできている?
- ☐ 滑りやすい床にマットを敷いた?
- ☐ 電気コードは保護・整理されている?
- ☐ 落ちやすい雑貨は撤去 or 固定した?
- ☐ 浴槽の水は残さず、ドアは閉めている?
- ☐ 侵入されたくない部屋の対策は万全?
前回の記事はこちら
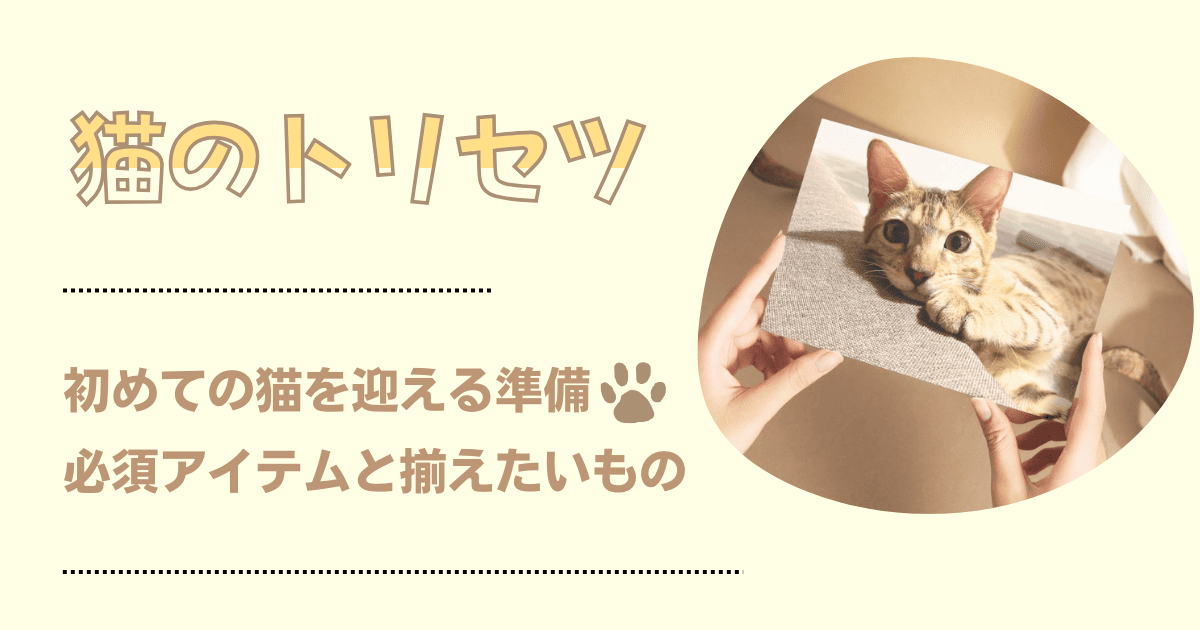
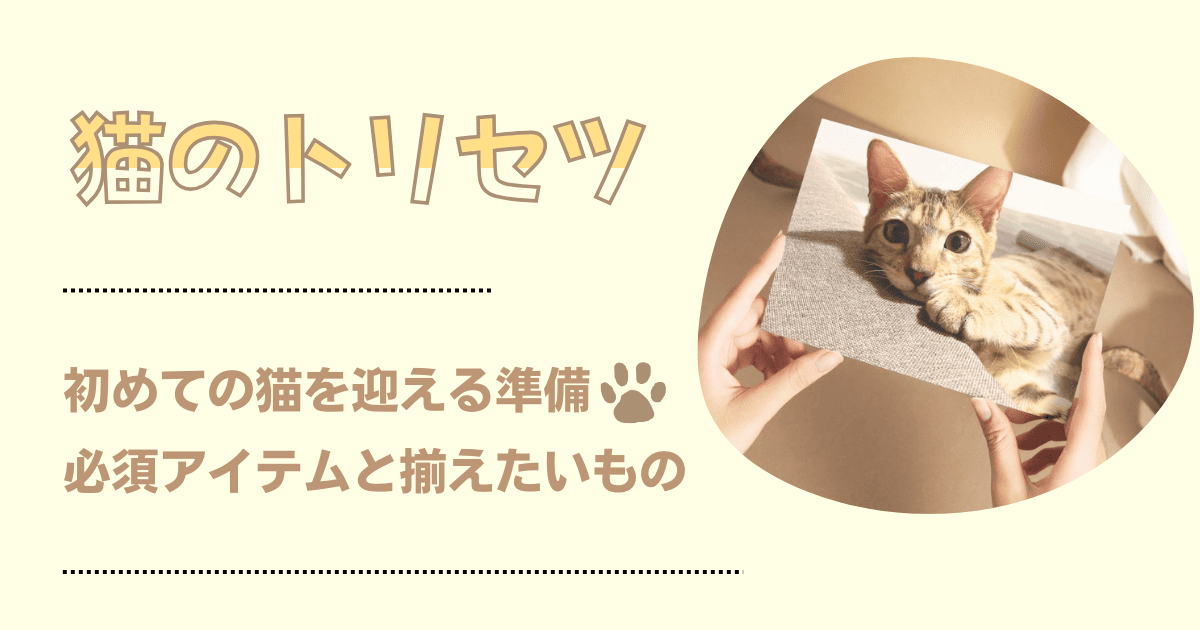
次回は、猫のための快適なレイアウトや動線づくりについてもご紹介できたらと思っています。