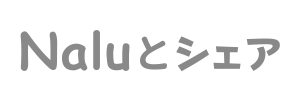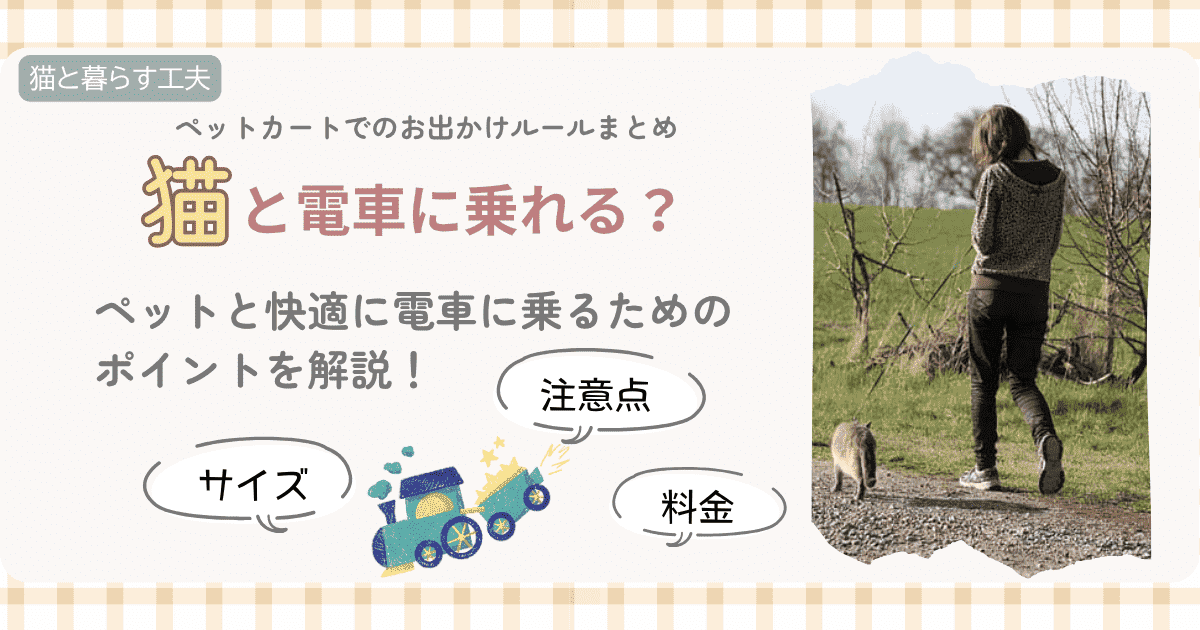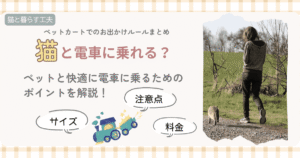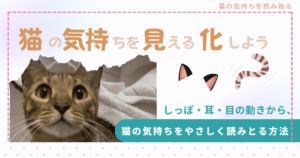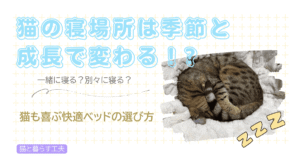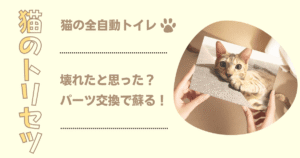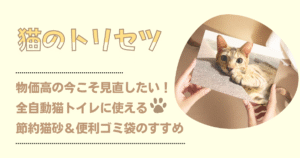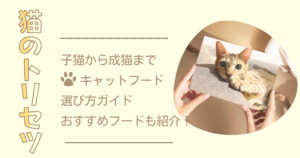ペットカートで電車に乗って、猫(もちろん犬も!)とおでかけできたら‥‥それってすごく便利で、ちょっとワクワクしませんか?
車がなくても、ペットカートで電車に乗れれば移動はラクラク。旅行や通院など、ペットとのお出かけの幅もぐっと広がります。
ペットと電車に乗るためには、周囲の人への配慮はもちろん、大切なペットを守るためにも気をつけたいポイントがいくつかあります。
この記事では、事前に確認しておきたいルールや注意点を、わかりやすくご紹介します。
ペットカートで電車に乗れる?
ペットカートで電車に乗ることはできます◎

ハンドルを押してラクに移動することができます。
ペットと電車に乗るときのルール
電車にペットを乗せるには必ず下記のルールを守る必要があります。
大きさや重さが限られていますので、猫や小型犬などの小さいペットとの乗車なら可能です。
- 猛獣やへびの類は、乗車が禁じられています。
動物専用のケースに入れること
- 容器に収納した重量が10kg以内であること。
- 3辺の最大の合計が120㎝以内の専用の容器に入れること。
- キャリーケース等から身体がはみださず、蓋が完全に閉まるもの
- ペット用スリング(布製だっこ紐)は全身が覆われていても乗車は不可。
乗車できるペットカートの条件は大きく分けて以下の2つ
- キャリー部分が取り外しできるタイプ
- キャリー部分のサイズが規定範囲内であること
電車に持ち込めるペットカートのルール
- キャリー部分が取り外しできるタイプ
ペットカートで電車に乗ることはできますが、基本的にはカートのままでは乗車できません。
電車内ではペットの入ったキャリー部分を取り外し、フレーム部分は折りたたんでおく必要があります。

カートのままでは乗れないケースが多い


キャリーを外し、フレームは折りたたむ
*キャリーの大きさにも注意
- キャリー部分のサイズが規定範囲内であること
ペットカートから取り外したキャリー部分が、各鉄道会社の持ち込み可能サイズの規定範囲内でなければ一緒に電車に乗ることはできません。
せっかくキャリー部分を取り外してもサイズオーバーでは、結局乗車できなくなってしまいます。
キャリー部分のサイズも事前に確認するようにしましょう。
JRや私鉄の共通ルール
- カートの骨組みは折りたたんで持ち込み
- 手回り品切符(290円)を購入する必要あり
- キャリーのサイズ:合計120cm以内、10kg以下
以下は、JR東日本・JR西日本・北大阪急行・阪急電鉄・阪神電車のペット(持ち込み品)ルールと公式情報ページの一覧です。
| 鉄道会社 | ペット持ち込みルール概要 | 公式情報ページURL |
|---|---|---|
| JR東日本 | 縦・横・高さの合計が120cm以内、重さ10kg以内のケースに収納。手回り品切符(290円)が必要。 | JR東日本:ペットの持ち込み |
| JR西日本 | JR東と同様に3辺合計120cm以内・10kg以内のケースに収納し、手回り品切符(290円)を購入。 | JR西日本:持ち込める荷物 |
| 北大阪急行 | 3辺合計120cm以内・10kg以内のケースに収納。ペットカートはケースと分離し、カートは折りたたむ必要あり。 | 北大阪急行:手回り品について |
| 阪急電鉄 | ペットはケースに完全収納(3辺合計120cm以内・10kg以内)し、ペットカートは分離して折りたたみ。手回り品料金(290円)が必要。 | 阪急電鉄:手回り品のご案内 1 |
| 阪神電車 | ケースに完全収納(3辺合計120cm以内・10kg以内)し、手回り品切符(290円)が必要。ペットカートは原則不可だが、駅員判断で可の場合あり。 | 阪神電車:営業案内(手回り品) 2 |
- 関東の私鉄では無料のところが多いです。駅でご確認ください。
それぞれの会社でルールは似ているようで微妙に違うので、事前に公式サイトで確認+駅員さんに聞くのが安心です。
猫と電車移動のコツ
- 混雑時間を避ける
- 体調の変化に注意
- 落ち着きがない、鳴き声などの対策
混雑時間を避ける
公共交通機関では、アレルギーの方や動物が苦手な方もたくさんいます。
お互いのためにもなるべく周囲の方とは離れた場所に乗るようにし、混雑が予想される時間帯を避けて乗るという配慮が必要です。
体調の変化に注意
電車に乗る前
ペットも乗り物酔いします。酔いやすいということが分かっている場合は、動物病院で事前に酔い止めをもらうことができます。
乗車中ペットにトイレはありません。(キャリーにペットシーツを敷くのがおすすめ)
- お気に入りのおやつを持っていく
- 乗り物酔いを避けるため、食事は乗車2時間前までに済ませる。
- キャリー内に、普段使っているおもちゃやタオルなど安心できるものを入れる
乗車中
乗車中は常にペットの様子を気にかけるようにしましょう。
暑さ、寒さ、乗り物酔い、水分補給にも注意が必要です。
- 嘔吐した
- 震えている
- 呼吸が荒い
- ぐったりしている
このような様子が見られた場合、すぐに下車して休ませます。
症状が治まらない場合は、お出かけを中止し動物病院に連れて行きましょう。
落ち着きがない、鳴き声などの対策
いつもはおとなしいペットでも慣れない場所へ行くと不安から落ち着きがなくなることも。ペットをキャリーケースから出すことは出来ませんが、おやつをあげる、優しく声掛けして頭を撫でてあげるだけで落ち着く場合もあります。
どうしても難しい場合は一度電車を降りてみて、犬の場合は改札を出て少し散歩してみると良いかもしれません。
無理強いするとお出かけ自体がイヤになってしまう可能性もあるため、その子のペースに合わせて柔軟に対応するようにしましょう。
ペットカートの選び方とおすすめ
- エアバギーなど電車対応モデル
- キャリー部分が取り外せるタイプ
AirBuggy for Pet
移動中も止まっているときも、ペットの姿勢がいつでもフラットになる”FLAT&GO”機能で大切なペットと一緒に快適なお出かけができます。
そのまま電車にも乗せられるサイズなので、いざという時のために持っていると便利。
MILA&LOUIS ペットカート
分離型と全体折りたたみ式の2way、PU耐摩耗車輪なので、衝撃吸収にも優れています。タイヤもスムーズで小回りがきいて安定感があり押しやすいです。
アイリスオーヤマ 犬用カート
こちらは我が家で購入したものです。(犬用ですがw)
ペットカート、ドライブキャリー、キャリー、キャリングカートの4WAYの使い方が出来ます。折り畳み収納も可能です。3輪なので4輪を求めている方はご注意ください。
個人的に段差への対応が楽なので3輪が気に入っています。
電車に乗せる時は以下の形式(キャリングカート)にし、ハンドルも短くし、120cmにおさまるようにしています。

まとめ
- 各鉄道会社でルールが異なるため、事前に公式サイトで確認+駅員さんへの確認が安心。
- ペットは基本的に3辺合計120cm以内・10kg以内のケースに完全収納が必要。
- ペットカートは折りたたんで持ち込みが原則。キャリー部分と分離できるタイプが便利。
- 手回り品切符(290円)が必要な場合が多い。
- 混雑時間を避ける・鳴き声対策・安心できるアイテムの準備など、ペットのストレス軽減も大切。
- 駅員さんや乗客とのやりとりも含めて、ちょっとした気配りが快適な移動のカギ。
- 電車移動はペットにとっても新鮮な体験。安全と安心を守りながら、楽しい思い出づくりを。
今回ご紹介したように、各鉄道会社にはサイズや重量、カートの扱い方など細かなルールがあります。
「ペットカートごと乗れると思っていたら、キャリーだけOKだった…」なんてこともあるので、事前に公式サイトで確認+駅員さんへの声かけは忘れずに。
そして何より、ペットにとっても電車移動はちょっとした冒険。
慣れない環境に不安を感じることもあるので、お気に入りの毛布や匂いのついたタオルなど、安心できるアイテムを用意してあげると◎です。